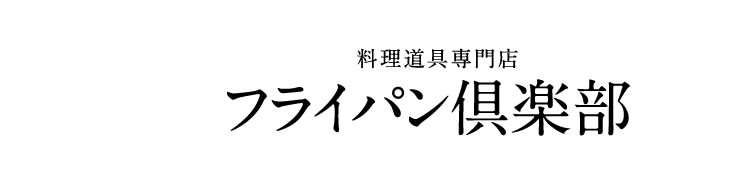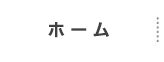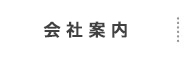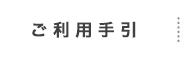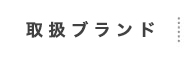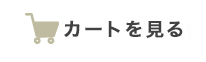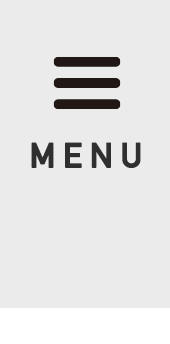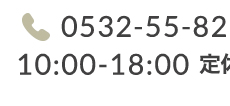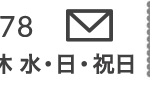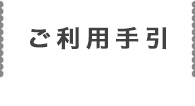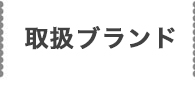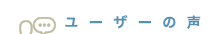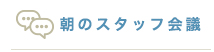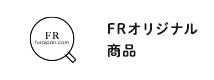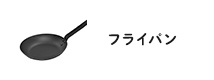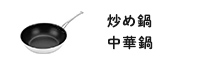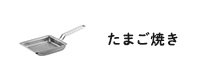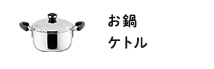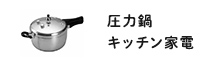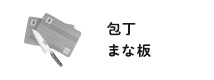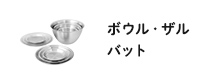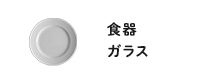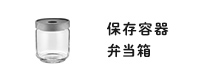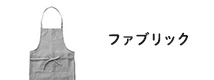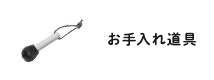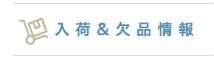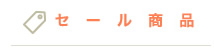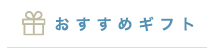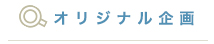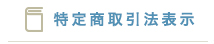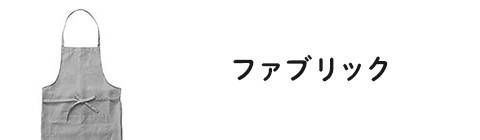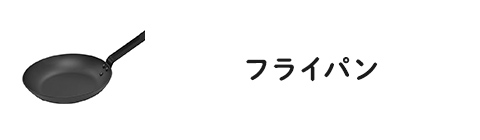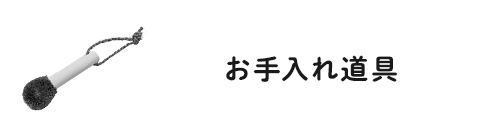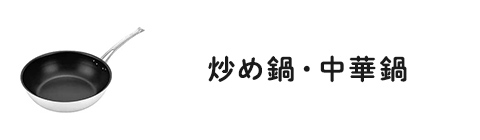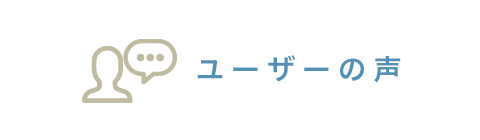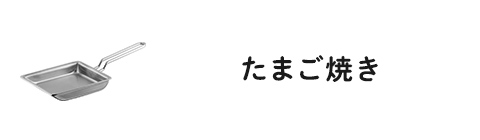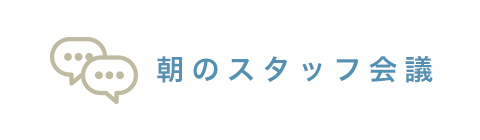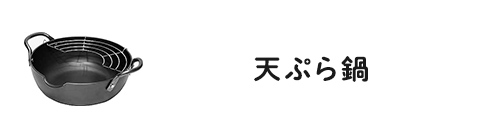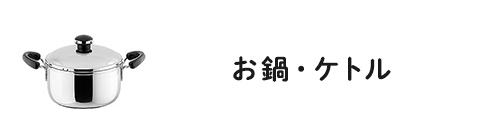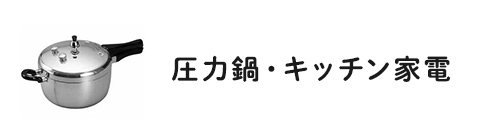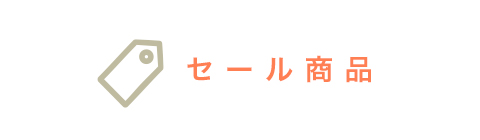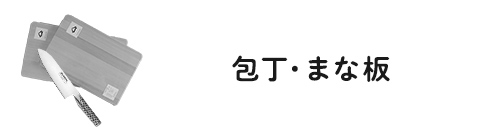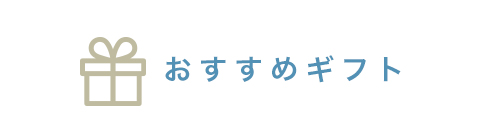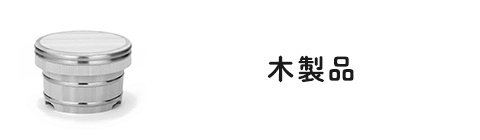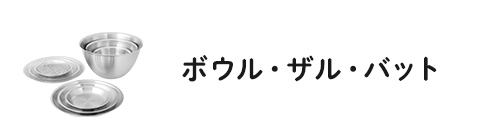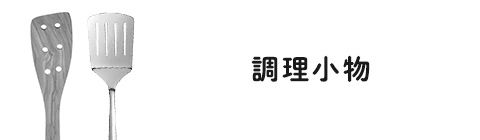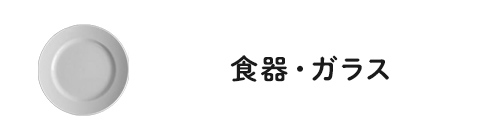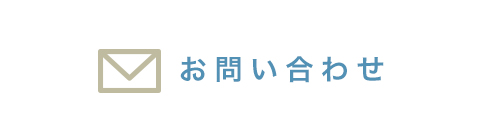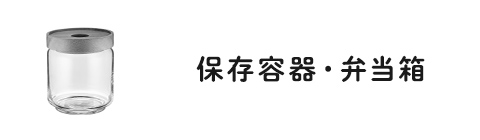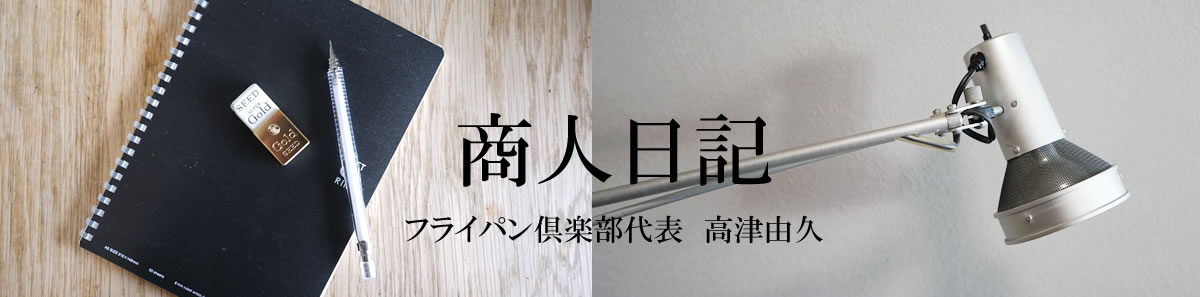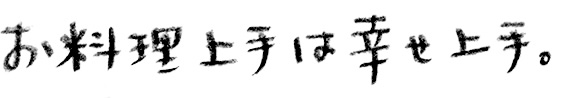流通の無言化
最近ユニクロをはじめとした小売店では、セルフ決済のみとなっています。
そんな時に、官僚でもあった堺屋太一さんが「流通の無言化」と表現していたことを知りました。
これが戦後の歴代内閣の基本方針の一つだったとのこと。
高度成長時代の官僚たちは、モノの生産に対して消費が追いつかない原因を考えた。
それは、小売店舗などで、お客さんと売り手が余計なおしゃべりに時間を浪費し、生産性を低いものにしているからだと。
これを批判していた先崎彰容教授は、その著書「知性の復権」で警察官であった作詞家阿久悠さんの父親の生き方を提示します。
「他者の視線を意識した『使命と倫理』こそが、一人の人間を人間たらしてめている。
使命とは、警官が求められる役割をこなすことであり、定義の枠外にでるのではなく、矜持をもって職責を果たすことです。」
生産性が優先される小売の現場にいる私には、この言葉が響いてきました。
警察官だけではなく、商人こそ、この使命と倫理を回復すべきではないのか。
昔の商店街にあった豊饒なおしゃべりを手掛かりに、復権すべき人間らしさを考えてみたいです。
2026月1月27日
裁判官の同級生
裁判官となった高校時代の同級生の活躍ぶりを小耳にはさんでいましたが、
最近は新聞紙上で拝見することに及んでいます。
数年前に東京大学前で受験生ら3人を包丁で刺した当時高校2年生の事件を担当していました。
私たちの高校時代とも重なりますが、学歴や偏差値の優劣で価値を判断しやすい風潮が背景にありました。
しかし、「人命軽視の姿勢は甚だしい。」保護処分ではなく懲役刑を言い渡します。
その上で「他人の命やあなた自身の命を大切にし、人生の希望を見つけて社会復帰してほしい。
裁判員、補充裁判員、全員からの気持ちです。」その言葉と裁判員制度に希望が見えました。
今回は、東京五輪の汚職事件の判決で、大物と呼ばれる被告に対して、有罪判決を言い渡していました。
賛否はおいて、司法の独立は守られていると思いました。
そして、2009年に始まった裁判員制度の定着にもご尽力されているのだと思いました。
それでも、最終的に決断する者の孤独や苦悩は深いと想像します。
しかし、それがあるからこそ希望は生まれる。
私も彼にならって、この世代の責任を微笑んで果たして参りたいです。
2026月1月24日
神戸のお父さん
弟の義理のお父さんが逝去されました。
お父さんたちは神戸の震災を経験されていて、また弟が婚約していた時に農作業で片腕を失う事故に見舞われました。
その事故の後に、結婚の挨拶で豊橋にご夫妻で来て下さいました。
伊良湖のホテルまで自動車でご一緒させて頂きましたが、明るくて前向きなご様子に安堵いたしました。
その後も、仕事だけではなく、お料理はじめ家事を率先されて行っていた。
そのお姿は、震災で傷ついた神戸の街と重なりました。
ちょうど三十一年目を迎えようとしていますが、「しあわせ運べるように」ふたつめの神戸市歌が心に響いて参りました。
「地震にも負けない」ことが、片腕を失っても負けないことにも通じます。
それは人生に起こる困難に負けずに明るく前を向くことを教えていたのだと気がつきました。
逝ってしまったお正月の優しい光は、孫たちに注いでいた優しい眼差し。
そんな孫たちの成長を見届けたタイミングであったのですが、
孫たちも「亡くなった方々の分も毎日を大切に生きてゆこう」と思いを新たにしたのだと思います。
そこに、しあわせ運ぶ未来を感じました。
2026月1月8日
視覚障害の女性と駅員
正月二日目の昼下がり。海岸近くのJR蒲郡駅ホームで電車を待っている時でした。
視覚障害の女性が駅員にエスコートされて一番後ろの車両が止まるところまで歩いて行かれました。
お二人は会話をされている様子はなく、直立したまま黙っていました。
女性は、杖を片手にお洒落なコートを着ていました。
駅員は、無心で任務を果たされている様子でした。
寒風が吹きすさぶ中で二人立つ姿に、とても大きな存在感を感じました。
その存在感はどこから来るのか。
それは、厳しい現実を前にしても、前を向いている姿に重なったのか。
その視覚障害を通じて、どんな過去があったのか。さまざま自分勝手に想像したからでしょうか。
その想像とともに、女性の背後にいるご家族の愛情が伝わってくるのです。
また、その一人を守ろうとする駅員のあり方にも、人として大切な何かを感じることができました。
同じく厳しい現実がある新年だとしても、前を向くようにとのエールに響いてきます。
それは新年の道標でした。助けを必要としている誰かに手を差しのばす新年でありますように。
また、あのお二人に幸多かれや。
2026月1月5日
人間性とは何か
AIをはじめとする簡単便利なモノが日常となる2025年でした。
ただ、本来人間は考える存在であるものの、思考停止となる危うさが潜みます。
その人間とは何か。あるいは人間性とは何か。それをつきつめていく必要があります。
例えば、電車や自動車は、人間の移動に大きな恩恵を与えていますが、
人間は本来歩く存在です。
その結果、現代人は歩くことをしなくなり、結果として健康を損ねています。
これからの時代は、人間性をつきつめて、簡単便利なモノを開発する、また使いこなすことが問われます。
その時、食べるという営み、その前にある料理するという行為には
人間性を育む要素があります。
それは、手を働かせることで、自分で考えて五感で感じることができるからです。
そこから、信じること、望むこと、愛することが育まれます。
それらを人間性とも表現できます。
そのため、料理することも、簡単便利なモノにすべてを委ねてはなりません。
自分の手を働かせることには価値があり、それは健康にもつながります。
2026年は、本質を見据えながら足や手を十分に働かせて、人間性の回復を目指したいです。
2025月12月27日
クリスマスの心
今年一年を振り返ると、お子さんが命を落とされたご夫婦たちのことが思い出されます。
同じ親として自分に重ねると、これほど心が痛むことはありません。
しばしばクリスマスに公演される、ヘンデルのメサイアの歌詞に
「ひとりのみどりが私たちのために生まれる。ひとりの男の子が私たちに与えられる。」
それはメシア誕生の約束であり、それが成就したのがクリスマス。
父なる神は、ひとり子なるキリストを与えて下さった。そこには親子の関係があります。
その時、子を失う悲しみを誰よりも理解しているお方が見えてきます。
そこにクリマスの心があると思いました。
そして、横田早紀江さんが娘のめぐみさんと別れて48年の重い歳月が流れています。
しかし、慰めは悲しみのあるところに溢れます。
そこには、心を痛めた人たちの真心が集まり、青いリボンの絆が生まれています。
日本国家には、自国の国民は自分たちで守る独立心を促している。
人知を超えた摂理を感じます。
そして、クリスマスは、私たち一人一人に、自分の生き方を問いかけています。
悲しみの向こうにある希望に気づいて参りたいです。
2025月12月19日
地域課題と商売
建築家・大島芳彦さんのリノベーションまちづくりの講演会が豊橋で開催されました。
懇親会では、大島さんから個人的に助言を頂きました。
通りというリニア(直線)で考えるのでなく、周囲の通りも含めた面で考えるとよい。
加えて、もっと自分のことを考えて、楽しみながら取り組むべし。
広小路通りは東西に延びた直線の通りで、私の店があるのは3丁目となります。
1丁目は飲食店が軒を連ねるようになり、3丁目界隈はマンションが建つ住宅街となっています。
同じ広小路でも、色合いが違いますので、通りや町名などの区分には気をつけたい。
かたや、自分の店のあり方を見つめ直す必要を感じました。
大島さんは「地域課題は不動産価値の卵」とも言われていたのですが、もともとの小売業は、地域課題に貢献できていたのだと思いました。
あわせて、自分の手でお料理をする価値を浮かび上がらせたい。
そんな自分の店の役割が明確になれば、楽しさが生まれてくることでしょう。
本質を見据えながら、小売業の原点に立ち返りつつ、地域課題に貢献できる商売を追求して参りたいです。
2025月11月16日
女の子とお姉さん
駅前大通りを歩いていると、歩道の真ん中で中学生の女の子がじっと下を見て立っていました。
近づいてみると、小さな鳥が動かずに伏せっていました。
それは「幸せの王子」に出てくる燕のようでした。
声を掛けると、「お姉さんがコンビニでビニール袋をもらいに行ったのを待っています。
それまで踏まれないように見ています。」道端で中学生とそのお姉さんが、
この小鳥を通じて出会い、どうしたらよいのかを話し合ったのだと理解しました。
それを知り、この二人の連携プレーに、さわやかな風が吹き抜けるようでした。
思わず「ありがとね」その場を立ち去ると、ビニール袋をもったお姉さんが私の前を急いで駆けていきました。
その後、二人がどうしたのかは見届けませんでしたが、丁重に拾い上げて、また二人で相談して、
どこかに埋葬したのではと想像しました。痛みを感じる中で、どうしようと迷ったものの、
二人の判断と行動に大切なものを教えて頂きました。
そして、その二人の出会いは偶然とは思えません。何か明日への希望を感じました。
私にも与えれている天の配剤に気づいて感謝して参りたいです。
2025月11月3日
旗をたてん
豊橋まつりで、わが街の広小路通りを練り歩く地元ダンスチーム「空(くう)」の後方で、大きな団旗がなびいていました。
これからの通りがどうあるべきか。青空のもとで、通りと旗がジャストフィット。
その時、慶應義塾の塾歌を思い出しました。嵐の中になびく旗を歌い
「樹(たて)んかな この旗を 強く雄々しく樹んかな」
この塾歌は、昭和15年軍国主義が強まる時代に発表されましたが、学問の命脈を絶やさないとの強い意思がありました。
慶應4年、近くの上野で戦火があがっても、福沢諭吉はウェーランドの経済書の講義をやめなかった。
すなわち、旗をたてるとは、たてる者の心意気、気概を示すことに他ならない。
それは、暗闇および嵐のような厳しい状況の時こそ、はっきりと表れるもの。
そして、たなびく旗は、あきらめないぞ、あきらめるなとのメッセージを発している。
通りとは、旗と一体となって、通りを行き交う人たちにエールをおくる空間でもあります。
その後、旗手の方とばったりお会いできて「ありがとうございます」私の想いと感謝をお伝えできました。
明日の広小路通りが見えた瞬間でした。
2025月10月20日
安売りの罠
地元の商業者の集まりで、スーパーの店長の名刺には、ディスカウントを手掛ける大手流通会社の名前が入っていました。
また、地元で活躍する食品スーパーが、大手スーパーの傘下に入ったと伺いました。
さらに、当地でも、ドラッグストアの新規出店が続いているとの報告。
これらの成長を求める波は、時代に合わせる判断もあるのでしょうが、何か大切なものが置き去りにされていると感じます。
経済成長の時代は終わり、少子高齢化の時代を迎えているのです。
ここで、気を付けたいのが安売りという見えない罠です。
安く提供することを顧客のためと位置付けているのですが、果たしてそれは真なのか。
価格競争に拍車を掛けて、事業者の首の締めあいとなってしまいます。
まともに競争が進めば、利益はないことに至ります。別の視点では、賃上げは遠くなるのです。
この時代は、顧客だけに偏ることなく、事業者のことを考える時でしょう。
そこを補完するのが商工会議所であり、公正取引委員会であり、公的な立場にある方々だと思います。
そして、小売業者は、競争から共創に方針転換をすべき時です。
2025月10月11日
宇沢弘文先生
本日ようやく涼を感じる日となりました。今年の暑さや自然災害は深刻であり、地球温暖化がますます加速しています。
そのために何ができるのか。物を作る現場だけでなく、物を売る現場でこそ貢献できることがある。
あるいは、物を売る現場が、できることをしていないので今日の状況を招いてしまった。
小売業者は、ここに本来の存在意義があるかもしれません。消費者ではなく、消費者の向こうに控える環境のことを考える。
それは、その場限りでなく、先の時代のことも考える。そのもとで、物の売り買いはされてしかるべきでしょう。
その時、1995年に「2025年には産業革命以前に比べて平均地表気温が2度上昇」と著書に記した宇沢弘文先生が偲ばれます。
当時より、炭素税などの地球温暖化対策を提言。同じく岩波新書「自動車の社会的費用」今日の日本社会への慧眼と感じました。
1942年に合衆国で出版された「ちいさいおうち」という絵本も、今日の世界を見透かしているようでした。
小売業者がこれら先人たちの教えを胸に、消費者に迎合するのではなく、消費者を先導することが問われています。
2025月9月19日
住民の反対運動
地元を通過する道路建設計画を受けて住民の間に不安が広がりました。
私も役員となる自治会では、通過決定後にようやく行政からの報告会を行い、さまざまな意見が飛び交います。
そこで、自治会としては異例のアンケートを実施します。
高齢者も多いため巡回して聞き取り、回収、集計、公表など時間と手間を掛けます。
その結果、反対意見が多く集まり、有志の寄付を募って反対運動を行うことに決まりました。
豊橋市のアリーナ建設の住民投票の事態とも重なります。
民意がしっかりと行政に伝わっていない。
行政としては、普段通りの手続きを進めただけかもしれませんが、
個人的には気が付いたら物事がすでに決まっていた印象でした。
かたや、市民が行政の取組に無関心であったり、住民自治意識も希薄になったりの課題がつきまといます。
このような事態を招かないように、常に関心を持たねばなりません。
反省とともに、街のことを考える好機のようにも思えました。
また、これからの反対運動を通じて関係者の皆さんとのつながりを深めることにも大きな価値があります。
そして、自分を成長させる機会としたいです。
2025月9月1日
五箇条の御誓文
戦後80年の終戦記念日を迎えて、戦争と平和を考える機運が高まっています。
昭和21年元旦に昭和天皇が発した、いわゆる人間宣言、新日本建設に関する詔書に帰ることが今日求められています。
「天皇を神とし、または日本国民は他より優れた民族だとし、それで世界の支配者となる運命があるかのような
架空の概念に基くものでもない。」その冒頭では、五箇条の御誓文を引用します。
「広く会議を興し万機公論に決すべし」云々、
民主主義は米国からの輸入ものではなく、明治天皇によって採用されたことが分かります。
わが国は、この民主主義を標榜して戦後復興を果たしてきました。
幕末に米国人ペリーが来航した時には、老中の阿部正弘が、諸大名や幕臣に広く意見を求めたことに通じます。
日本の国柄は、この民主主義のもとにある自由そして独立です。
先の戦争では、その自由が失われて軍部の独走を招いてしまった。
戦争と平和の問題はもちろん、さまざまな社会問題も、広く会議を興しみんなで話し合って決めていくこと。
その原点に帰ることは、昭和天皇はじめ先人たちも首肯されることでしょう。
2025月8月19日
太き骨の先生
平和を語る時は、よく言葉を選んで、慎重でなければなりません。
正論であっても、そこに心がなければ、正論たりえず。
人間は、理だけでなく情もある。言葉では納得できても、感覚で納得できないこともある。
先の戦争の被害が甚大であり、その傷は深いものがあります。
それは、地上戦となった沖縄や被爆地の広島・長崎だけにとどまらず、
無差別空襲のあった日本全国の都市でも同じです。
戦争経験者は少なくなっていますが、その戦争経験者と触れ合った最後の世代が私たちです。
祖父母たちの悲しみや苦悩をそれとなく感じてきました。
そのもとで、心を使って考えることができる。また、より冷静に議論ができる。
首相が広島の地で紹介された歌が心に響きました。
「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」
原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑に刻まれた歌でした。
先生を慕う健気な子供たちの姿に心が痛みます。
そして、先生は、子供たちを守れなかったことをどれほど悔やんだことでしょう。
それは、先生だけではなく、今を生きる私たち一人一人のあり方を問うています。
2025月8月7日
住民投票を終えて
豊橋市で初めて住民投票がありました。ここに至るまでに市議会の議員の皆さんには、さまざまなご苦労があったと思います。
本来は、市議会で決めるべきことを市民に丸投げした等、市民からの批判は厳しかったことでしょう。
しかし、最終的に、結論を出して頂けたことは、成果だと思いました。
もちろん、ここに至ってしまったことには、議会はもちろん、行政も市民も反省すべきところがあるでしょう。
ただ、前向きにとらえれば、住民投票を通じて市民の当事者意識は涵養されたと個人的に感じました。
豊橋市の総合計画の基本理念は「私たちがつくる未来をつくる」であり、
現市長も「自分たちのことを自分たちで決められるまち」を掲げています。主語は市民です。
そんな時に、豊橋中央高校の甲子園出場が決まりました。偶然とは思えず、大人たちが主体的に動いていれば、子供たちはそれに答えてくれる。
子供たちからのエールのようでした。今月の「とよはし市議会だより」で議員の皆さんの集合写真が表紙を飾っていました。
対立を越えた笑顔に、なんだかうるっと来てしまいました。議員の皆さん、お疲れ様でした。
2025月8月1日
首相の覚悟
参議院選挙で自民党大敗とありましたが、与党での過半数までには、ほんの少し届かなかった状況です。
無所属議員を呼び込めば過半数には到達します。
その点で大敗とまで表現するのはどうかと思いました。
また、消費減税に触れなかった点では、善戦したと感じます。
しかも、政治と金の問題に関わる自民党議員たちが、自分たちが決めた首相を退陣に追い込むのは合点がいきません。
折しも米国との関税交渉の真っただ中にあり、与党として一致団結して国益を最優先する姿勢を見せてこそ
国民からの理解を得ることができるように思います。
だからこそ、自民党は変わらなければならないのかもしれません。
選挙期間中に首相がトランプ大統領に対して「なめられてたまるか」の発言に胸のすく思いがしました。
選挙結果に対して「ここから先は、いばらの道だ」この覚悟こそ、トランプ大統領に向き合うのに相応しいと感じました。
そして、多くの国民が、首相の覚悟を感じているからこそ、石破やめるなのデモが起こっています。
退陣することだけが責任の取り方ではありません。石破頑張れと首相にエールを送ります。
2025月7月26日
モンゴル訪問
ここ豊橋では、アリーナ事業の賛否を問う住民投票があります。
賛否の二者択一は、分断が生じます。
この分断は、わが街だけでなく、他の市町でも、あるいは世界でも広がりを見せています。
そんな時、天皇皇后両陛下が、モンゴルを訪問されていました。
雨降る中で、日本人死亡者慰霊碑前で頭を垂れていました。
旧ソ連により、モンゴルでは約1万4000人が強制労働に従事し約1700人が抑留死したと言われます。
駆けつけた遺族の鈴木富佐江さんは御年八十八。
陛下が言葉を掛けられました。「お父さまがお亡くなりになって、ご苦労がおありでしたね。」
前を向いた鈴木さんは取材に答えていました。
「モンゴル抑留にはほとんど日が当たっていなかった。みなさんに知っていただいて光栄です。」
さながら、陛下のお姿に、東奔西走する宮沢賢治の「雨にも負けず」が重なりました。
そして、世界をよく見聞きして、自分にできることを誠実に行うことだよと示しているようでした。
やがて、それは分断の橋渡しをする平和への道となる。他者を想い、あわてず、あせらず、あきらめず進んで参りたいです。
2025月7月10日
戦後を死語に
アリーナ事業の賛否を問う住民投票が近づく中で、街の未来を考える集まりが地元校区市民館で開催されました。
地元の松山小学校の同窓会長の立場もあり、今校長が生徒たちに伝えている校章の話をさせて頂きました。
それは、吉田藩主であった大河内松平家の家紋であった蝶がデザインされていること。
今回のアリーナの建設予定地は、豊橋公園、すなわち吉田城址であり、改めて豊橋公園のあり方が問われる。
その時、校章が歴史を顧みることを促します。
ちょうど、豊橋美術館では「終戦80年 軍都豊橋の面影展」が開催。
その展示は、縄文時代から始まっていました。
そんな時、日本経済新聞の直言欄で保阪正康さんが戦後を死語にしようと語っていました。
「この言葉を使っている限り、1945年から後の日本の歴史はいつまでたっても(太平洋)戦争の時代との比較でしかなくなる。」
戦前、大正、明治はいざ知らず、江戸まで俯瞰してこそ見えてくるものがある。
7代当主の松平信明が、当時のロシアと向き合いますが、そこには自分の国は自分で守る気概がありました。
すると、自分の街は自分でつくる呼び声が響きます。
2025月6月26日
豊橋空襲
当店のある広小路通りで本日はじめて清掃活動を始めます。
その目的は単に通りを綺麗にすることだけではなく、3つの目的があります。
地域で友達を作ること。ただいるだけでいい場所を作ること。地域で活動を始める人を応援すること。
図らずも本日は、80年前に豊橋空襲があった日と重なります。
この通りにあった百貨店が米軍の爆撃目標でした。
この通りを中心に市街地は2時間半余りの爆撃で廃墟と化しました。
死者は624人、全焼全壊は1万5886棟と記録が残ります。
生き延びた人たちの悲しみ、苦しみ、痛みは想像を絶しますが、
前を向いて今日の街を少しづつ作り上げていきます。
5年後には、みんなで助け合う広小路発展会が発足して、通りに「広小路通」のネオンが灯ります。
その時の理事長が私の祖父であったことを数年前に知ります。
また、この日に実施するのは、明日の夜に通りで開催される歩行者天国に出店する人たちを応援するためでもありました。
きっと先人たちも、未来の大人となる私たちを応援するために汗をかいてきたのでしょう。
作業の後には、コーヒータイムがあり、先人たちを偲びつつ会話を楽しみたいです。
2025月6月20日
石垣島からの名刺
地元の工務店さんより、新たなリフォーム事業でご指名頂き調理道具を購入頂きました。
その時、ある名刺を出して、この方をご存知ですかと問われました。
驚きました。その方は、二十年以上前から親交のある元取引先の方で今日も年賀状のやりとりがあります。
もとは東京在住で、定年後はたこ焼き屋になりたいと言われていました。
また、立教大学の卒業生で、立教愛なるもの感じていました。
娘さんが引きこもった時、転職された時、独特の毒舌と苦虫を見せるのですが、常にユーモアがあるのです。
そして、漂着した地が石垣島。
実は、その工務店のお客さんの同僚が石垣島に観光に出掛けて、乗り合わせたタクシーで豊橋から来たと伝えると、
当店のことを紹介されて、その名刺を渡してくれたとのこと。たこ焼き屋ではなく、タクシードライバーでした。
今年の箱根駅伝では、立教大学の健闘が光りました。すぐに結果が出ずとも、ひたむきに走り続ける。
そのことが重なり今年の遅れた年賀状に「立大生のように歯を食いしばって走っています。」
すると、その名刺は、島崎藤村の椰子の実のようであり、走る私への声援に響きました。
2025年5月31日
井上成美
五月の連休に横須賀からご来店のお客様がいました。
いつもはお電話でのやりとりでしたが、初めてお会いすることができました。
横須賀の長井という地区の女医さんで、その地区は最後の海軍大将と言われる
井上成美さんが晩年を過ごしたところでした。
それが、阿川弘之さんの「井上成美」で紹介されていました。
井上さんは海軍兵学校の校長でもあり、敵性語とされる英語の使用を禁止する空気が漂う中、
「英語を話せない海軍士官では、世界に通用しない」日独伊三国同盟には異を唱える。
終戦後は、一切の公職から身を引いて慎ましい隠遁生活に。
ただ、地域の子供たちに英語を教えていました。
阿川さんの本の書き出しは鮮烈です。「晩年、東郷元帥をどう思うかと人に問われて、井上成美は、『人間を神様にしてはいけません。神様は批判出来ませんからね』」
終戦の日には、一日何も食べず、海をじっと眺めていた。
女医さんによると、井上さんのことを知る方も高齢となりますが、未だ語られているようでした。
「ずっとお店に行ってみたかったのでとても嬉しかったです。」お礼状を頂き
井上さんの生き様を思い出しています。
2025年5月23日
ショーザフラッグ
元米国国務副長官リチャード・アーミテージ氏がご逝去されました。
同盟国の友人として、自分の頭で考えることを促していたと感じます。
それは外交官や政治家だけではなく、国民一人一人に対するものであり、晩年も慶應義塾の若者に呼びかけていました。
すなわち、同じ独立した国家であれば、責任が伴うことを自覚せよ。
誰かに依存するのではなく、自分の足で立て。恐れるな、君たちは立てるのだと。
それが、米国同時多発テロ時に日本に向けて発言されたとする「ショーザフラッグ」(旗をみせろ)
イラク戦争時に日本に求めたとされる「ブーツオンザグラウンド」(観客席ではなくグラウンドに立て)
そこにある国家としての意思、主体性こそ、戦後の日本人が鳴りを潜めてしまったもの。
読売新聞紙上の評伝には『「日本自身で答えを」貫く』とあり
「6次にわたる対日提言(アーミテージ・ナイ報告書)でも『日本の国益のためには日本自身で答えを探さねばならない』という
日頃の口癖と同じ姿勢だった。」トランプ大統領を前にして、アーミテージ氏の声が響いてくるようです。
日本よ、ショーザフラッグ!
2025年4月28日
東三河フードバレー
レモン農家の河合浩樹さんが主宰する「美食倶楽部初恋レモン」にゲストとして参加させて頂きました。
17年続く集まりで「4年ほど前から東三河フードバレーの中に組み込みながら、
フードクリエイターの聖地を背景にして活動しています。
生産者や食に関係する人をゲストに迎え、食の問題などを話し合いながら、食事を楽しんでいます。」
ちょうどその日は、中村ナス園の中村敏秀さんが白い茄子をご紹介下さいました。
そんな地元農家の食材を生かしたエムキャンパスフードグループ高木章雄料理長のお料理を頂きます。
しかも、多士済々の皆さんと談笑しながら楽しめる豊かで贅沢な時間でした。
東三河フードバレーとは「まずは、東三河の豊かさに気づいてもらいたい」と
推進するサーラグループの若手社員の声に共感いたしました。
発酵研究家の廣西紘子さんは、予防医学に取り組まれていて、その要諦を伺うと「足るを知ること」だと。
それは、豊かさに気づいた結果、それを分かち合い、それを未来に繋いでいこうとすることで体得できるもの。
この時代この世界が必要としているものでした。
2025年4月19日
街の灯
街路灯の行政手続きをするために、歩いて市役所に出向きました。
完了するまでに、煩雑な手続きがあり、何となくすっきりしない心持ちの帰り道。
桜咲く神明公園に入った瞬間でした。
母子連れの小さな女の子が背後から「こんにちは!」と声を掛けてくれました。
そして、無邪気に私のそば近くに来てくれました。
私は少し驚きましたが、挨拶を返したものの、少々戸惑いそのまま歩みを進めました。
すると、「どこに行っていたの?」と投げかけてくれました。ようやく振り返り「市役所に行ってきました。」
「市役所って何?」すると恐縮していたお母さんの説明が入りました。
女の子は、そばにあった遊具に乗って遊び始めたので「声を掛けてくれてありがとう!」と別れました。
ほんの数秒の出来事でしたが、「ねえ、元気を出してよ。」との激励の声のように響きました。
私の心は、晴れ晴れと明るくなっていたのです。
その時、世界名作劇場の「ポリアンナ物語」を思い出しました。
ポリアンナの明るさが、街を明るくする物語。その女の子と重なりました。
街の灯とは、街路灯だけではありませんでした。
2025年3月29日
先生の幸せ
広小路通りで活動する私の写真入りの記事が、地元の中日新聞で紹介されました。
すると、中学校1年生の時の担任の先生が、卒業アルバムと当時の学級通信を鞄にしたためて店まで駆けつけてくれました。
「新聞を見ましたよ。」微笑んだお姿は、当時のままでした。
わがことのように嬉しそうに、私の当時の想い出も語ってくれました。
それは、朝早くからの学校行事で見守りに立つ先生に対して「ご苦労様です。ありがとうございます。」
労をねぎらう挨拶を私がしたことだったと。
私は全く記憶にはありませんが、挨拶を評価してくれたのです。
しばらくして、母校の松山小学校で、同窓会長として児童たちの前でお話しする機会がありました。
それは、先生を大切にして下さいとのお願いでした。
先生は、卒業後もずっと自分を忘れず見守っている。
自分の幸せを願ってくれている。44年後に駆けつけてくれた恩師のことも紹介しました。
そこで、児童たちに投げかけました。
「今度は、どうしたら、先生は幸せになれるかを考えましょう。」
そして、私の回答を披露しました。それは、生徒の自分が幸せになること。
2025年3月22日
三河武士
豊橋三田会で、明治生命の創業者である阿部泰蔵の後裔の方とお会いすることができました。
阿部さんは、もともと新城市鳳来町上吉田の豊田家の出身であり、今日もその生家は残っているそうです。
その豊田さんが、福沢諭吉と三河とのつながりを教えてくれました。
福沢諭吉は、大分の中津藩の出身ですが、その中津藩の藩主が奥平家。
その奥平家は、長篠の合戦時に長篠城主でした。
武田軍に城を囲まれても死守して織田・徳川連合軍の勝利に貢献します。
その時に名を馳せたのが、奥平家の家臣であった鳥居強右衛門(すねえもん)。
織田・徳川の援軍が来る情報を決死の覚悟で自軍に伝えて、自らは武田軍に捕縛されて磔刑にて落命。
辞世の句は、我が君の命に代わる玉の緒の何いとひけむ武士の道。ここに三河武士の源流を垣間見ます。
それを知る福沢諭吉は、幕府と維新後の政府に仕えた勝海舟と榎本武揚を
この三河武士を例にあげて痛烈に批判します。
「家のため主公のためとあれば必敗必死を眼前に見てなお勇進するの一事は三河武士全体の特色」
それは、現代のわれら三河人にも語っています。今こそ、三河武士を見よや。
2025年2月24日
備えられた30年
日本商工会議所で3期9年会頭を務めた三村明夫さんの講演が当地でありました。
「失われた30年からの復活」と題して、人口減少社会への提言をされていました。
GDP(国民総生産)の経済指標で測れば、失われた30年です。
しかし、働き方改革をはじめ、環境への対策、公共への貢献などGDPとは違った指標で企業経営者たちは取り組んで来ました。
また、人口減少を前にして、内部留保を積んできたことは、ある意味では、ワイズスペンディング(賢い支出)に通じます。
それは、時代を見据えた経営判断でもあった。
ところが、GDPだけで評価すれば、企業経営者の心は萎えてしまう。
そこで、伊藤邦雄教授が提唱するESG経営などの公益に関わる指標が叫ばれます。
その手がかりが、私益と公益との両立を求めていた渋沢栄一翁の精神です。
30年のど真ん中を歩んで来たわれら世代は、時代の変わり目で奮闘しています。
失われた30年ではなく、備えられた30年として、自信を取り戻すべきでしょう。
三村大先輩のメッセージの核心は、心の復活だと思いました。
この30年を踏み台にして、誇り高く花を咲かて参りたいです。
2025年2月18日
現代の志士
富士市の吉原商店街エリアで奮闘する鈴木大介さんとお会いしました。
昨年、商店街の老朽化した共同ビルの一角をリノベーションして分散型ホテルを開業。
分散型ホテルとは、フロント、客室、食堂等のホテル機能を分散させて、
宿泊者が街を回遊することを想定しています。また、同じくリノベーションしてゲストハウスと
唐揚げ屋も運営。さらに、まちづくり会社の役員として、新規開業事業者をサポートしています。
そのエリアでの新規開業事業者は、この10年で130を越えるとのこと。素晴らしい数字です。
そして、商業的の外側にチャンスがあると。
それは、事業者の世界観を出店を通して表現する経済合理性では測れないもの。
そこにある創意工夫にあふれた活動のエネルギーが、この時代に求められているのだと。
やわらかい公共とも表現していましたが、私としては、商人こそ本来そのエネルギーに満ちた存在であると思います。
これまでの商業的なものを越えていくこと。このようにお互いを響かせ合う人が同志です。
そして、同志が出会って日本が動く。幕末の志士と重なりました。
2025年2月11日
オデュッセウスの智慧
憲法学者の山本龍彦さんの著書「アテンション・エコノミーのジレンマ」に希望を感じました。
市民から自由を奪う怪物であるリヴァイアサンは、今日は国家ではなくて、
デジタル空間を席巻するプラットフォーマーだと。
新たな怪物は、人間からアテンションを獲得するために刺激的で魅惑的な情報やコンテンツを流し続ける。
その結果、人間の欲望が膨らんで、自分で選ぶ自由を奪われてしまう。
かたや、自由意思は虚構とする認知学者の下條信輔さんとの対談は、この著書の白眉でした。
山本さんの手がかりは、オデュッセウスの智慧でした。
ギリシャ神話で、セイレーンという怪物の美しい歌声を聞くと、聞きほれて船が遭難してしまう。
そこで、船乗りのオデュッセウスは、自分の体をマストに縛り付けて、セイレーンに遭遇するものの
無事に航海を終えることができた。このように、理性が働いている時に対策を施しておくこと。
そこで、ガンダムの主人公アムロの言葉を引用します。「人間の知恵はそんなもんだって、乗り越えられる!」
信じること、そして望むこと。それも弱き人間が授かった力です。
2025年1月31日
健全なデジタル空間
今日のデジタル空間は、不健全な側面が色濃くなっています。
それでは、健全なデジタル空間とは何か。不健全と思われる側面をあげて整理します。
まず、匿名がまかり通ること。それは責任の欠如です。誹謗中傷は多くの場合、匿名のもとで行われます。
そこで、当店ではレビュー投稿時には名前をお願いしています。
その上で、こちらからのコメントを添えた掲載に努めます。
次に、正確性が問われないこと。それは信頼の欠如です。
そこで、当店では、借り物の言葉ではなく、自分で実際に使ってみた言葉を大切にしています。
分かりやすさとともに、前後の文脈も意識して誤解のない表現に努めます。
そして、意図されずに行われること。それは自由の欠如です。
操作や仕組みが複雑になっているために、本人の意思が二の次にされる傾向があります。
そこで、当店では、分かりやすい仕組みを優先して、簡潔な説明を心掛けて、必要な場合は、その都度許可を頂くことに努めます。
以上の責任、信頼、自由の先に、健全なデジタル空間があると考えます。
そこに、安心安全な価値あるお買物が実現します。
2025年1月24日
ひとりに
デジタル化がますます進展する中で、新年を迎えました。
仕事には対象があり、それは人間です。仕事の本質とは、ひとりの人間に対して向き合うこと。
ひとりを思い、ひとりの幸せを願うこと。小売業での小とは、このひとりの人間を指していて、
これを理解している人が商人かもしれません。
私がお世話になる九十を越えた理容師さんは、同業の息子さんに、このことをよく諭すのだと言われていました。
小売業に関わらず、あらゆる仕事は同じだと思いました。
ただ、それは、結果として手間暇をかけることになります。非効率かもしれません。
かたや、デジタル化とは、手間暇をかけないことでもあります。効率は良くなる。
年始に挨拶状を書きましたが、内容面印刷をデジタルで行い、宛名と一言を手書きで添えました。
その名前から、その人自身を思い浮かべ、その人の新年の幸せを願う。
しかし、相手の負担になってはならない。そのあたりの距離感も弁えたい。
このような人間を大切にした心通うデジタル化が求められています。
新年ご来店頂くひとりのお客様に、真摯に向き合って参りたいです。
2025年1月17日
ドキュメント72時間
「ちょっと、お料理でもしてみようかな。」そんな気持ちが芽生えるお店でありたいです。
こちらからの良いことの押し売りではなく、ご本人の意思を尊重することが小売業の大前提です。
そんな自由の余地が小売業の現場では確保されているだろうか。
年末にNHK「ドキュメント72時間」年間の振り返りが放映されていました。
そこには、カメラを72時間置き続けるだけで、制作者側の筋書きはありません。
何が起きるかは分からない。しかし、そこには撮影対象者の気持ちを引き出そうとする制作者の見えない声掛けがあります。
不思議とカメラの前でも気持ちを出すことができる。
それは、真剣に向き合っている制作者の存在が大きいのだと思います。
しかも「こうするといいよ」との提言はなく聞き続けるのみ。
そこで、撮影対象者は、自分で自分の答えを見つけているかのようです。
これは、商人と顧客との関係とも重なります。
商人は、見えないところで、顧客の気持ちを引き出して、ご自分に相応しい商品を選んでもらう。
そこには、顧客の自由意思を尊重する態度があります。買物の主役は、顧客です。
2025年1月6日