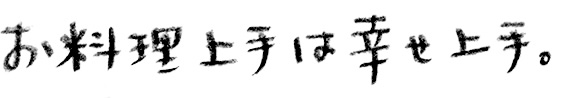加熱講座18 味の染みこみ
ポトフやおでんでは、どうしたら具に味が染みこむのか。 結論としては、ゆっくりと冷める時に、味は染みこんで行きます。 その反対に、加熱することは、鰹節や昆布で出汁をとっている時のように、食品から味が引き出されています。 ですから、加熱後がポイントとなります。 よく言われるのは、「一晩寝かせたカレーは美味しくなる」 この寝かせることにも通じるでしょう。 また、厚手のお鍋で、余熱を生かして、そのまま放置しておくことも、この点で理があります。
その冷めて行く過程で、まず周囲の煮汁から温度が下がって行きます。 そのため、具と煮汁に温度差が生じて、温度の高い具から煮汁に向けて水分が出て行きます。 さらに、その穴をうめるかのように、煮汁に含まれる塩などの味成分が、具の中に浸透して行くのです。 これが味の染みこみです。 ところが、量が少なく、または板厚が薄いお鍋であれば、冷めるのが早くなる。 その結果、煮汁の味成分が具に入って行く時間が不足してしまい、味が染みこみにくくなります。
その点では、少量よりも沢山作った方が美味しくなる。 また、保温性の良い厚手の鍋が美味しくなる。 その結果、ゆっくりと冷めていくので、具に味が染みこんで行きます。 加えて、ホット・キルト等の保温カバーを使うと良いでしょう。 これを鍋に被せることで、放熱を防いで、鍋内の保温力が良くなり、ゆっくり冷めることに通じます。 そもそも、食材が美味しくなる温度と時間は決まっていますが、100度以下がほとんどであり、 ぐつぐつと沸騰を続けることではありません。
その点でも、沸騰したら、そのままホット・キルトに入れておけば、お鍋が自然と料理をしてくれます。 煮崩れることもなく、素材そのものの味を生かします。 さらに、エネルギーの有効利用にも通じます。 そこには、資源を慈しむ感謝の心が伴います。実は、その感謝の心があってこそ、美味しさは生まれてくるように思います。 すなわち、工夫して慎ましく加熱していく。 そのようなあり方は、美味しさばかりか、美しい生き方にもつながることでしょう。

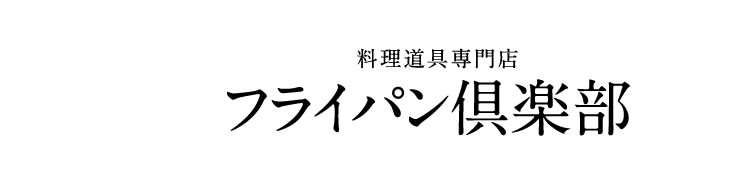



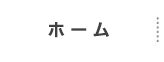
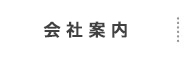
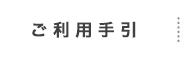
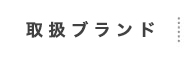
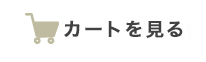

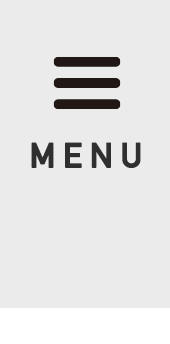
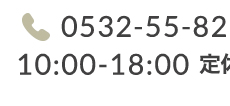
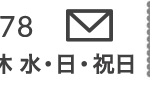
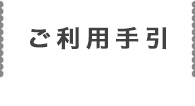
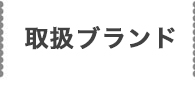



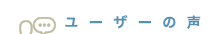

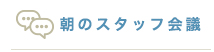

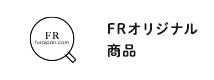
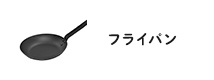
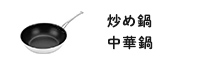
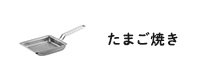

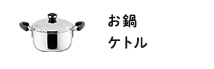
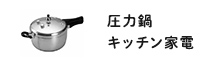
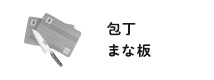

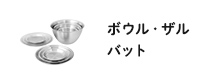

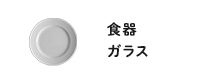
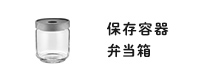
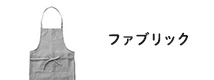
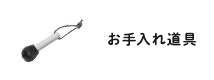
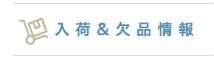
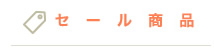
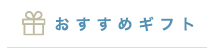
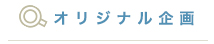

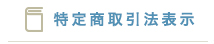



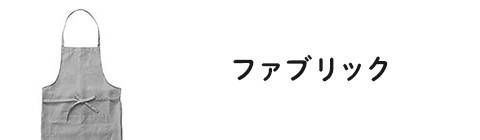
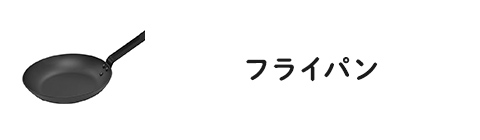
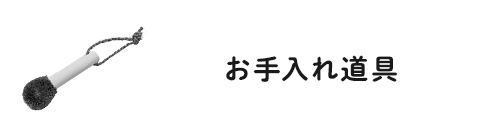
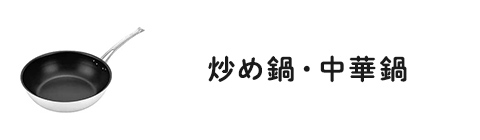
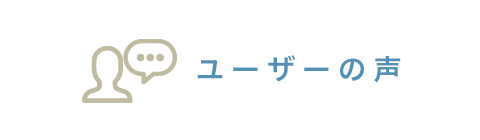
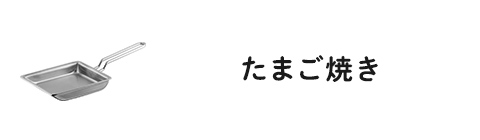
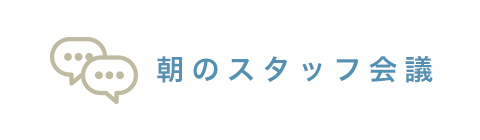
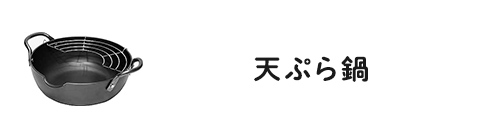

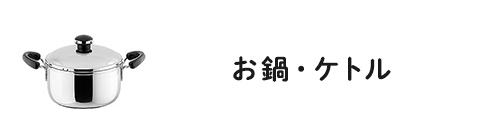

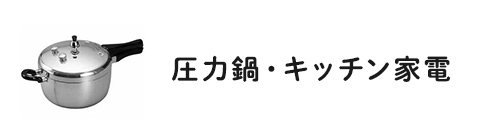
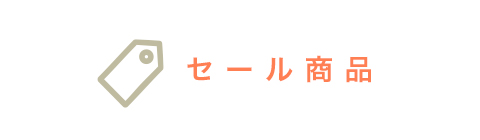
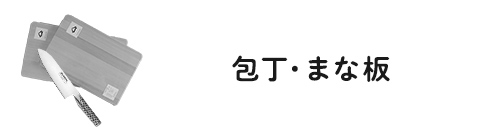
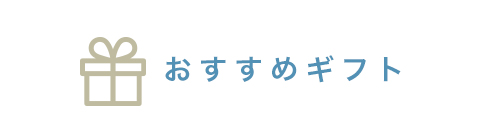
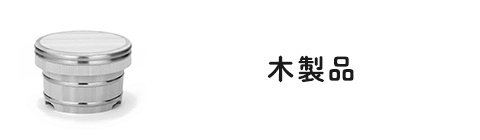

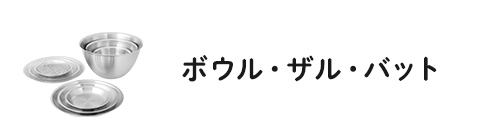

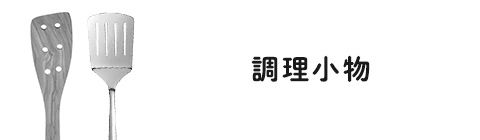

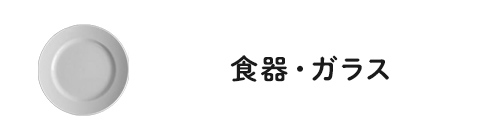
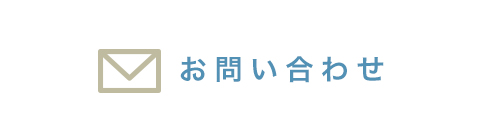
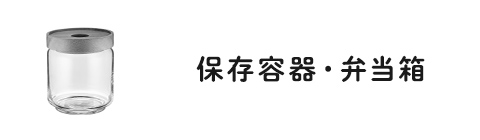
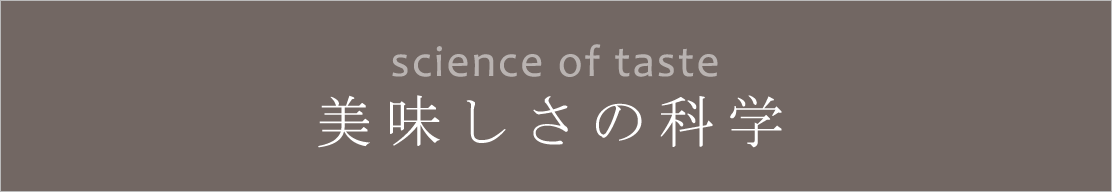
 無駄な加熱をせず、適温調理を実現するホット・キルト
無駄な加熱をせず、適温調理を実現するホット・キルト