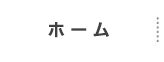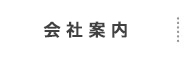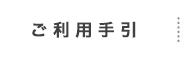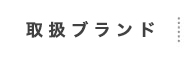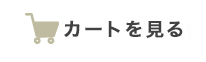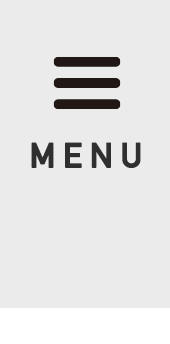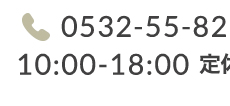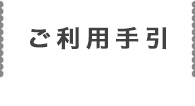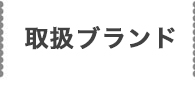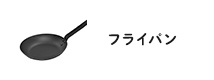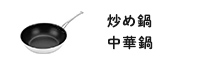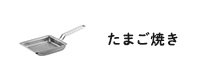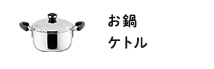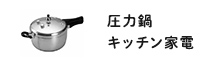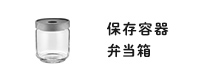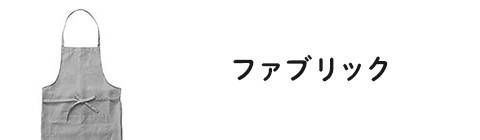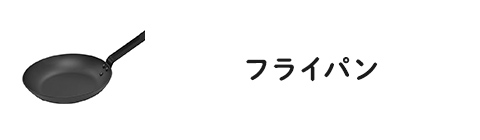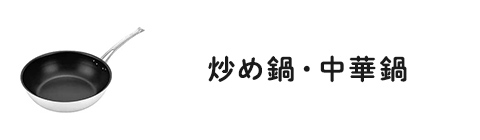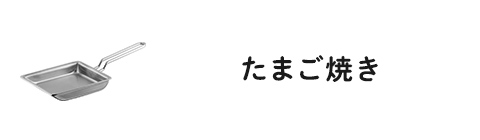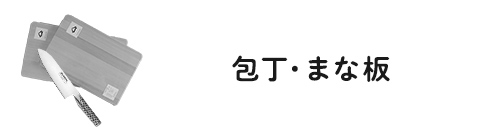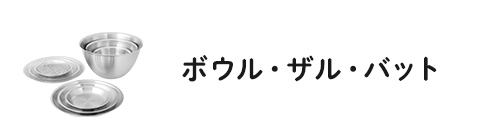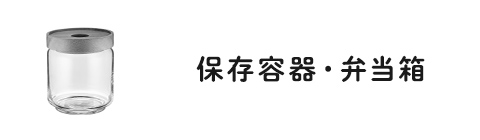台所が、教室だった
「幸田文 台所帖」(幸田文著・青木玉編 平凡社)に「台所」というタイトルの随想があります。 著者の幸田文(あや)は、小説家・幸田露伴(ろはん)の娘で、露伴から生活技術を教え込まれます。 その教えがちりばめられた文章を通じて、先人たちの家事にまつわる哲学を伺い知ることができます。 果たして台所とは。
 「幸田文 台所帖」(幸田文著・青木玉編 平凡社)
「幸田文 台所帖」(幸田文著・青木玉編 平凡社)
幸田文は、波瀾万丈な一生を送られたようですが、かぞえ14歳から48年間立ち続けた台所という場所を表現しています。 「公開のような、また自分だけの密室のような、不思議なところである。」 確かに、その場所は、家族の誰からも見られるオープンな場所でもあります。 ダイニングと一体となったオープンキッチンであれば、なおのことでしょう。 かたや、密室とは、ご自分の心と重ねていました。 「料理という公開の作業にかくして、欲もうらみも、不倫も嫉妬も、冷淡も憎悪も、 女ひと通りの業をさらしていたのは、いなめないのである。 それ故に私はあそこで、我慢のあとの安らぎを、悲しみのあとのやさしさを、憎悪のあとの責め、 嫉妬のあとのむなさしさを教えられたのではないか。 そこは大根や魚を料(りょう)るところであったが、女の心の業をこなす場所でもあった。教室だったと思う。」 齢六十一での心境を綴っています。
台所は、基本的に一人立つところであるがゆえに、自己を省みるところと言えるでしょう。 その意味では、食卓から離れていた昔の台所は、それなりの理があったようです。 そこでは、食材を切って、食材を水に晒して、食材を火にかけるという、いわゆる料する行為を通じて、 自分の心も深く切り刻んで、それを晒しているかのようです。 さらに、そんな状態から美味しくなっていく姿に我が身を重ねて、自分の心も軌道修正されて、整えられていくとも言えるでしょう。 「いま私は、ようやく静かな台所にいる。四十八年が必要だった、静かで平安な台所である。」 それは、悟りを得たようにも見えてしまいます。 いつも教えられて来たのだけれど、それに抗う自分がいた。 そして、ようやく、まな板の上の魚のごとく、すべてを調理人に委ねるような境地に至ったようにも受け取れます。 私たちも、その高嶺の途上にあるのかもしれません。
その途上では、自分の現実に圧倒されてしまい、自暴自棄になったり、逃げ出したくなったりするのも私たちの現実です。 ところが、台所という場所には、不思議な力が潜んでいるようです。 私たちと同じ幸田が台所に立ち続けることができたのは、「女の心の業をこなす」が手がかりのようです。 こなすとは、辞書では、かたまっているものを細かく砕くとあります。 業とありますが、私たちの硬い心を砕いてくれるのは、他者からの愛情なのでしょう。 それは、食材に向き合うことで、農家や漁師の方をはじめ、食材の背後にある方々の苦労が身に沁みます。 さらに、自分のために料してくれた母親や祖母などの苦労が身に沁みて、その苦労が自分のためであったことにも気づかされます。 そこに感謝が溢れて、今度は自分が与える者に変えられる。 台所に立つとは、注がれた愛情に感謝して、他者のために愛情を注ぐことなのでしょう。
「業をさらしていたのは、いなめないのである」とは、真摯に自分を見つめる姿を垣間見るようです。 それは、お料理が愛情を注ぐことであると言う認識があったゆえに、浮かび上がって来たものだと思われます。 そこには父親の愛情をはじめ、幸田が受けた愛情の厚みを感じます。 注がれた愛情という神聖なものに照らされて、はじめて自分の現実に気付けるのでしょう。 そして、自分の現実が分かるほど、他者には深い愛情を注げるようになる。 また、それでも硬くなってしまう心に対して、料理の根幹でもある煮炊きの繰り返しが待っています。 それを通じて、日々わが身を省みることで、しだいに心は柔らかくされて行く。 そんな毎日を通じて、人は少しづつ成長していくように思います。 幸田が四十八年を必要したとありますが、それは生涯続くのでしょう。 「台所が、教室だった」その幸いを噛みしめて、今日も台所へ、いざ行かん。