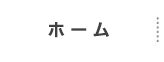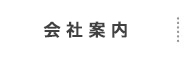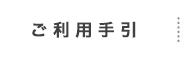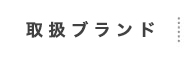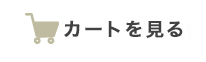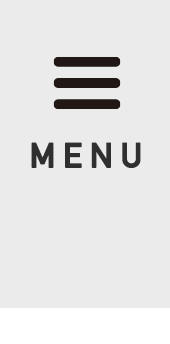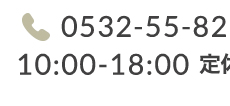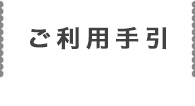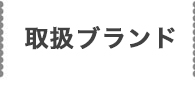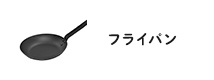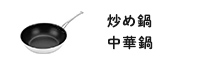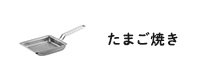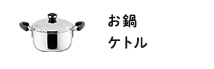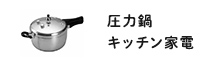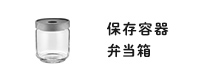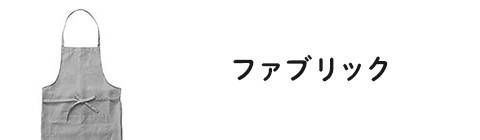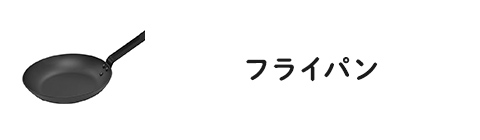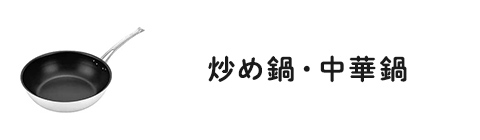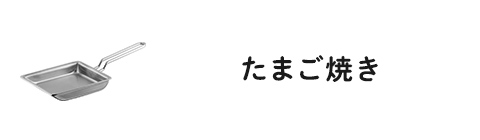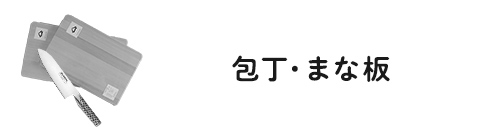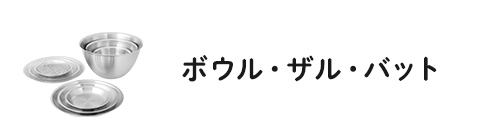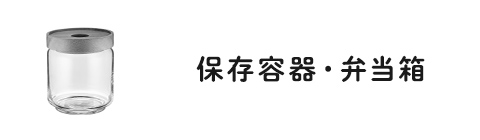食を通じて育まれる責任と愛
「春がまた来るたび、ひとつ年を重ね、目に映る景色も少しずつ変わるよ。」 シンガーソングライターの竹内まりやさんが「人生の扉」で 「五十になるとnice、六十になるとfine、七十になるとalright、八十になるとstill good、しかし、 九十以上生きる」と英語をちりばめながら歌い上げます。 年を重ねるごとに開く人生の扉は重くなるのですが、 年をとっていく姿を美しく豊かに表現しています。 年を重ねるごとに、見えて来る景色が違って来る。 いや、今まで見えなかったものが、見えてくるようです。 その高みにあるのが九十なのでしょうか。 このたび、九十になられた辰巳芳子さんの「食に生きて 私が大切に思うこと」(新潮社)を読んで、 この歌を思い出しました。辰巳さんも、こんなことを綴っています。 「もう九十歳になった私が、いまにして思うことはね、人間、五十代なんてまだ 人間のことは何も分かっていないな、と。つくづくそう思う。」 そんな九十を生きて到達した食の境地を提示してくれます。
 「食に生きて 私が大切に思うこと」(辰巳芳子著・新潮社)
「食に生きて 私が大切に思うこと」(辰巳芳子著・新潮社)
まずは、お母さんの浜子さんの思い出からはじまります。 やはり、母親あっての辰巳さんであることが分かります。 ご自身そのように言われることには少々抵抗がおありのようですが、 抗えない真実のように、結局はお母様のことに筆が行ってしまうようです。 特に、私が印象に残った浜子さんは 「ん、これでいいでしょう。」という味を決める時の潔い態度。 辰巳さんも、そんなお母様を見てこう語ります。 「味を決める。それを繰り返していると、判断力、決断力が磨かれて、 しかも瞬時にそれを行使できる、そういう人間になっていく。」 そして、夫婦のあり方です。 ご主人が亡くなる少し前に、お母様は娘に語ります。 「これからの私の務めはお父様が死を恐れないようにさしてあげることだ。」 そんな覚悟のもとで、ある日ぽろっと打ち明けます。 「私は身体を使い切ってしまった・・・・・」 このような妻を持ったお父様も「人生は簡潔に」をモットーに生きる誠実なお人柄であったようです。 お母様というよりも、正確にはご両親あっての辰巳さんでした。
そんなご両親に留まらず、お祖父さんのことに話しは及びます。 時代は奇しくも、近代日本の夜明け。 お祖父さんは、軍艦を設計する技術者。 いかに、近代日本が、自国の独立を守ろうとしたのか。 お祖父さんの生涯は、日本が自国の軍艦を作りあげた歴史でもありました。 まずは、軍艦をもつフランスから学びます。 フランス語を習得して、その文献を読み込み、そして、フランスまで赴いて学ぶ。 当時の学問への取り組みは、現在の比ではない壮絶なものを感じます。 そして、明治維新から30年も経ない短期間で、日清戦争の黄海海戦で 勝利する軍艦を建造してしまう。そんなお祖父さんの最後が印象的でした。 お世話になった方を臨終の場に招いて、ワインをふるまって乾杯。 家族一同はそれをじっと見守っていた。 子供心に辰巳さんは、そのことを昨日のことのように覚えているとのこと。 洒落た別れの告げ方に、粋(いき)を感じます。 そんなお祖父さんを、侍という言葉で表現しています。 私はその侍の血を引き継いでいるのだと。
そして、結婚してすぐに戦地に出掛けて、帰らぬ人となったご主人を語ります。 また、その後病んでしまう辰巳さんも、また戦争の犠牲者でした。 父親からは、相手が無事に帰ってから式を挙げるようにすすめられますが、 それを知った相手がぽろっと一粒涙を落したと聞きます。 辰巳さんは、父親のすすめを押し切って、すぐに式を挙げる選択をします。 その決断は母親譲りだと思いました。 しかし、その後もその決断が正しかったのか悩みます。 戦後50年を迎えた年に、テレビで野ざらしにされた日本兵の映像を見て、ようやく解答を得ます。 「ああ、やっぱり帰ってくるのを待っていますというだけでなく、 ちゃんと結婚してあげたから、ちゃんと彼の側にいてあげることができたなと思って、 あの判断はあれで正しかった、あれでよかったんだと思った。」 これも、50年目にして見えた世界なのかもしれませんが、 ほんの数週間しか一緒に過ごせなかった夫婦であっても、 ご両親以上に素晴らしい夫婦だと私は思いました。
そこで、戦争と食との関係を掘り下げます。 ご主人が戦地に行く時は、もはや日本には物資も少なく戦争ができる状態ではなかった。 「腹が減っては戦はできぬ」この時代は、もはや通用しなかったようです。 あるいは、食の価値をよく理解していなかったのかもしれません。 表現を換えれば、食の価値を分かっていなかったために敗戦に至った。 日本兵の75%が戦死と言うよりも餓死だったと。 徳川家康をはじめ、戦を知る戦国武将たちこそ、 食の価値をよく把握できていたのかもしれません。 禅寺でも典座という料理長のような務めがあり、お料理が最も重要な役目として、 特に高徳の老僧が選ばれることも紹介しています。 わが国では、そのような食に価値をおいた歴史があることを指摘しています。 それなのに、先の戦争では、いつしか、大砲、軍艦や飛行機などの武器の方に価値がおかれて、 それを操縦する人たちの食がなおざりにされてしまった。 それは、食糧自給率が下がったままの今日の日本にも通じると警告を発します。
戦後を生き抜く中で、さまざまな方との出会いがあります。 ちょうど10年間の闘病生活の時期とも重なっていたようです。 その一人、慶応義塾の印東(いんどう)太郎先生から心理学を学びます。 「人間の出来と言うのは、すべて生きていきやすいような仕組みになっている。 忘れたいようなことは、ちゃんと忘れるようになっている。 だから、人を許せるようになっているんですね。 そういう話を聞いたということが、非常に私を生きやすくしてくれましたね。 病気と真っ向からぶつかって闘うのではなく、その自分の体の仕組みを信じて 闘病できたからね。」そんな出会いがあったのも、必然であったようにも思えます。 こんな事も語っています。 「自分のほうから求めて仕事を探したことも、わざわざ仕事を作ったことも、ない。 ただ、私にめぐってきた仕事だけ、神様が『やれ』とおっしゃた仕事だけを、 ひたすら真面目に、自分にできる精一杯にやってきたんですよ。 その積み重ねが現在の私になっている。」 生きるとは、何か自然なもののようです。
最後に、再度お母様の浜子さんが登場します。 改めて食とは、代々受け継がれるものであることが分かります。 「長い時間軸にわたって私たちは先人と全部つながっている。」 今回の本は、辰巳さんの出会いの物語とも言えます。 「先人のいのちがけの営みのおかげで、私たちはいまこのように食べ、 生きて行くことができる。だからね、私たちもこのいのちをより良い方向に進化させて、 次の世代に渡していく責任があるということなのよ。」 私なりに、食は「いただきます。」という感謝を生むのだと思います。 すると、天とも呼ばれる、宇宙・地球・大自然を与えてくれた偉大な創造者を求める、 さらには信仰する敬虔な気持ちが生まれます。 かたや、恵みや愛を一杯にいただく卑小な存在である自分自身の価値にも気づきます。 それが根のところで分かった人は、次代への責任を自ら負って行けることでしょう。 そのあり方が愛することであり、愛するように人間は仕組まれている。 その愛こそ、九十を迎えた辰巳さんの境地なのでしょう。