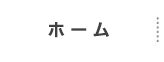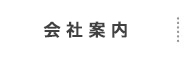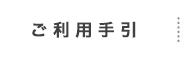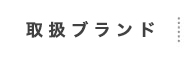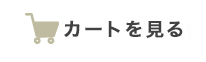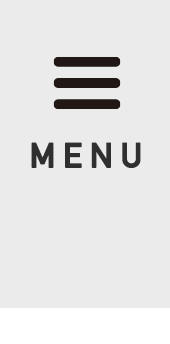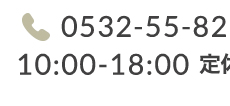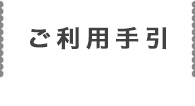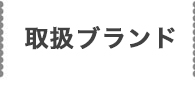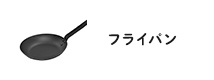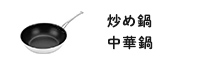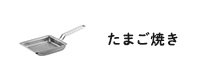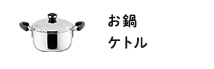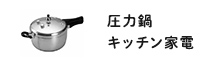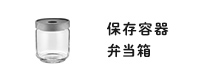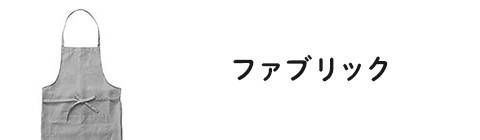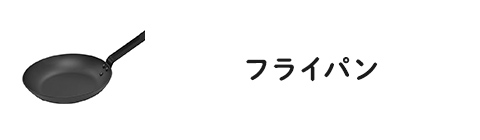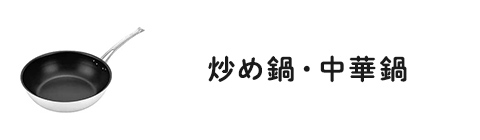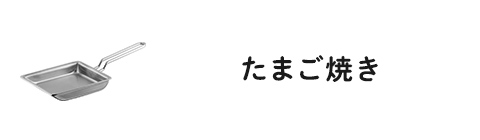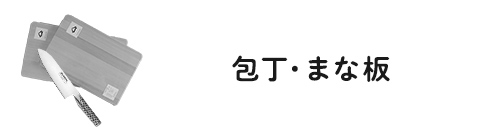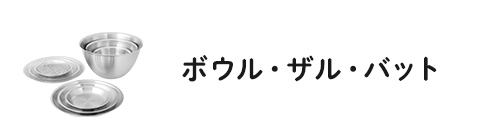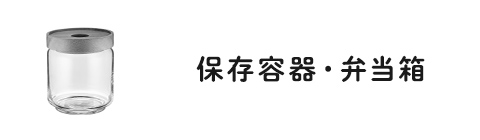kaicoの会 九州の巻 旅日記
先月10月1日、父親から会社を引き継ぎ、4代目の社長に就任しました。 当社の創業は1910年ですので、100年以上の歳月を重ねて今日に至ったことが分かります。 取引先をはじめ関係者の皆さんに挨拶状を送ると、こんな声が届きました。 「継続することの難しさと尊さを痛切に感じるこの頃です。 変わらないようでいて、次々と新しいものが生まれているのが世の中で、 的確な判断力と創造力をともなった適応力が求められます。 それだけに、継続力には感服します。」 そんな声をいただいて、100年の歴史の重さを感じました。 そして、先週末フォームレディーさんが主催するkaicoの会という、 メーカーの方、卸の方、小売の方、加えてユーザーの方が一堂に会する 集りが、焼き物の街である有田・波佐見でありました。 昨年は高知で開催されましたが、 こちらのページも参考下さい。 明日のわが業界を語り合う稀少な集りでもあり、昨年に続いて参加させていただきました。 今回の旅では、当社の代替わりのタイミングもあり、継続することの難しさや尊さを強く感じるものでした。 その視点で旅を綴ってみます。
 有田・波佐見に続いて、長崎・熊本に向かいました。夕闇せまる長崎港です。
有田・波佐見に続いて、長崎・熊本に向かいました。夕闇せまる長崎港です。
今年は、有田焼が始まって400年目の記念の年でありました。 100年どころではなく、その400年という歳月には圧倒されます。 まず、最初に訪れたのが、泉山磁石場(いずみやまじせきば)でした。 ここは有田焼の原料となる陶石の採掘場であり、1616年朝鮮人陶工・李参平(りさんぺい)により発見されて、 日本磁器発祥の地となりました。 そこには、100年続いてきた会社が今後目指していくべき手がかりがありました。 それは、400年ずっと、この発祥の地を覚えて来たことです。 有田焼を継承して来た人々は、ここに来て、先人たちの思いを感じとって来たことでしょう。 そして、そこは水墨画が広がるような美しい山の中にあり、私たちが販売する食器は、 そんな自然の恵みから生まれてきたことが分かります。 それは、陶工あるいは人間の技と言うよりも、まずは大自然の恵みがあってこそと、 私たちを謙虚にさせてくれます。 いつしか、人間の作り出した文化が讃えられて、そのベースにある資源をはじめとした 自然の恵みのことを忘れてしまいがちです。 その恵みに感謝していく。そんな謙虚さが有田焼の継承者にはあったのでしょう。
午前10時30分に福岡空港に集合。 そこから大型バスに乗り込んで、泉山磁石場を訪れた後に、 同じく山の中のある龍水亭という川魚料理店でお昼をいただきました。 こちらのお店も創業1921年で100年近い歴史をもっていました。 ここでは、お料理もさることながら、その器一つ一つにも深い味わいがありました。 もちろん、どれも藍色の器、染付の有田焼でした。 同行されていたデザイナーの小泉誠さんの著書「地味のあるデザイン」を思い出しました。 地と図を分けて、地という背景の中に図が浮かび上がってくる。 これまでのデザインは図が重視されたが、地が重要であると。 今回、この染付の器こそ地であり、それが図である料理を引き立てていると思いました。 そして、この季節の青い空を思ったのですが、写真を撮る時にも、 この青い空が地となると、その対象物が映えるのです。 ふと、私たち販売員は、図である商品を生かす地のような存在だと思いました。 そして、私たちの人生も、自分だけではなく、周りの誰かを生かすことこそ本来のあり方なのかもしれません。 有田焼からは、そんなメッセージも聞こえてくるようでした。
実は、私の到着した時間が遅かったので、特別に自動車を手配いただき大型バスを追いかけました。 その運転手が、マルシゲ陶器の花田さんでした。 花田さんは、社長の甥御さんです。 少し前まで埼玉で働いていましたが、つい最近故郷に戻られて、叔父さんの会社を将来継がれると伺いました。 そこには、強い覚悟とともに、故郷有田への愛情を感じました。 あるいは、故郷が花田さんを引っ張ったのかもしれません。 そして、花田さんのお兄さんも、会の世話役となって下さって昼食時に同席となりました。 お兄さんも、ほぼ時期を同じくして、大阪から故郷に帰ってこられて、 行く行くは有田の器を紹介する仕事をしたいと語ってくれました。 お兄さんの方は、小さなお子さんもおられて、こちらに戻ることは、 生活のこともあり、周りから強く反対されたそうです。 しかし、賛成してくれたのは奥さんだったと伺いました。 そんな思いをもっている人たちがいるからこそ、有田焼があるのだとも思いました。 この若いお二人に出逢えたことは、私にとって素晴らしい巡り合わせであり、 故郷で働いて生活する同じ立場の者として励まされました。
その後、波佐見の窯元を見学いたしました。 土からロクロ等で成形して、一旦素焼きをします。 これである程度硬くなります。 続いて、呉須(ごす)という絵具で絵付けをして、釉薬を塗って焼成します。 その過程を分かりやすく紹介いただきました。 私も愛用しているambaiマグを作っていた光玉陶苑の太田さんが、 デザイナーの小泉さんとのやりとりを紹介してくれました。 小泉さんのデザイン通りにすると、焼成すると取っ手が少し落ち込んでしまう。 少し傾けて焼くなど、そのためにいろいろと工夫されたそうです。 小泉さんは、作り手に難しい要求をされることがあるようですが、 結果として、当初は無理だと思われることも出来てしまう。 その作り手の力を引き出す要素があるように思いました。 多分、小泉さんは、作る現場のこともよく心得ていて、 それができるギリギリの落としどころを直感的に理解されているように感じました。 また、そこにはデザイナーと作り手の信頼関係が伺えて、 良いものを作ろうとする気持ちのところで、お互いに一つになっているのだと思いました。 そこには、物作りに真摯に取り組む熱い情熱を感じました。
 ambaiマグは独自の釉薬で作られていて、その風合いの魅力が理解できました。
ambaiマグは独自の釉薬で作られていて、その風合いの魅力が理解できました。
吉村陶苑さんでは、吉村さんが私たちに心情を吐露してくれました。 作り手と売り手は運命共同体であり、悲しみや喜びをともに分ちあう存在だよと教えていただいたようでもありました。 そして、寂しげに「後継者がいなくて困っています。」 かといって、そこには地元ではないところから修行に来ていたお弟子さんがいました。 吉村さんは、その方も紹介してくれて「彼は道を間違えた。」と冗談を飛ばしながら、 ご本人はそれを否定されていました。 その言葉の背後には、この道はそんな生易しいものではないぞと優しく諭しているようにも感じました。 そして、「後継者がいない」との言葉の真意は、地元で生まれ育った存在であり、 責任をもって会社の経営までしてくれる存在のことを意味していたかもしれません。 あるいは、自分の窯元だけではなく、有田・波佐見の全体のことを考えた上での言葉だったようにも思われます。 その言葉の背後には、400年続いて来たものへの畏敬なり、強い思い入れを感じました。 かといって、それをご自分もずっと取り組んで来て、 それを継承して生活して行くことの大変さも熟知されているのでしょう。
ようやく乗り込んだバスの中では、広島県福山市にある若葉家具の社長である井上さんと同席いたしました。 井上さんの会社も、名のある府中家具の伝統を受け継いでいます。 しばらく建築のお仕事をされていて、その後ご実家にお戻りになった。 また継承話に花を咲かせていると、「流れ」で今日に至ったと表現されていました。 それは、私たちの意思を越えたものとも言えるでしょうか。 運命とか宿命とかのニュアンスにも近い。 先ほど、私も「故郷が引っ張った」という表現を使いましたが、そこには 故郷の家族や友人なども含まれていると思います。 自分を育ててくれたことへの恩や感謝も含まれていると思います。 井上さんの「流れ」という言葉には、自分の趣向や感情を越えた、 人とのつながりあるいはご縁を大切にしていることを感じました。 井上さんは、木に親しんでいただこうと、家具だけではなく、ちょっとした木製品の雑貨も制作されています。 それらは、あくまで、木を知るきっかけにして欲しいとの思いが込められています。 売ることの本質を掴んでいる姿を垣間見て、井上さんは天職を得ているようにも感じました。
宿泊地の嬉野温泉に着くと、窯元の皆さんも10名程駆けつけてくれて親睦会が始まりました。 私もその場で、自分の思いを打ち明けました。 「適正な価格で売りましょう。価格競争ではなく、違ったところで切磋琢磨しましょう。 ともに力を合わせて行きましょう。」 すると、小泉さんの呼びかけで、50名近くの参加者が円陣を組みました。 「カイ」「コー」とみなで声をあわせました。 さらに、場所を変えて、深夜3時まで話は尽きないのです。 その時、kaicoの製造メーカーの社長と隣合わせとなり、またも後継者談義。 社長も、ある会社で働いていて生活は安定していたそうです。 ところが、父親の製造会社を継ぐことを決意する。 それは、先行きは不透明な状況が付いてくることでもありました。 その時、奥様が「やってみたら。」と同意してくれたのだと。 その言葉が、今日の社長を支えているようでした。 そして、「ここにいる人たちは、悲しみを知っている。」 酔いがまわっている社長からは、そんな言葉も出て来ました。 同じ問題や悩みを共有できたゆえなのでしょう。 悩みがなければ、これほどの結束はないのかもしれません。
翌朝は、ひとり長崎に向かいました。 嬉野温泉から高速バスに乗り、1時間ほどで長崎駅前に到着。 長崎に引っ張られたようでした。 それは、今回の旅のテーマである継承することをさらに深めることもでありました。 個人的に一人の日本の信仰者として、長崎および浦上こそ、日本の信仰の発祥地とも感じて来たのです。 浦上の信者たちは、有田焼と同じく400年間信仰を継承して参りました。 江戸幕府の禁教政策の中でも、隠れキリシタンとして、脈々と信仰が受け継がれる。 幕府からの過酷な弾圧は、浦上一番崩れ、ニ番崩れ、三番崩れと連綿と続きます。 明治政府になっても、浦上四番崩れ、浦上村のすべての村民が流罪に処せられて全国に散らばります。 明治6年に信教の自由を獲得して浦上に戻りますが、さらに苦難は続きます。 今度は原爆の爆心地となり、ほとんどの信者は命を落として、浦上は焦土と化す。 それでも、浦上の人たちは、信仰を継承して来ました。 私が訪れた日曜日も朝6時から始まり1日4回もミサが執り行われて、 日本のカトリック教会では最大規模の信徒が集まる姿を目の当たりにしました。
平和公園を訪れたのは、月明かりのある夜でした。 誰もいない爆心地の碑のそばに、千羽鶴が幾重にも吊るされていました。 それを目にした瞬間に、涙があふれて来ました。 そこには被爆国の日本人としての強い意思、情念のようなものを感じました。 それは、一つ一つ手を使って折り込んでいかれたもの。 その手を感じました。 すなわち手の仕事を通じて、その真心や強い意思が表出されるのでしょう。 すると、折り鶴と同じように、有田・波佐見の器にも平和への願いが込められているように思えてきました。 私たちが扱う料理道具や食器とは、まさに平和の象徴でもあるのかもしれません。 そして、平和とは何であるのか。 浦上の人たちは、平穏無事そのものを求めたのではなく、 苦しくとも、それに立ち向うことを求めました。 そこにこそ生きる実感、生きる手ごたえがあるのだと思います。 すなわち、平和とは、何もおこらないこと、何もしないことではなく、 厳しく難しい状況があっても、それを避けることなく果敢に挑み、自らの手を使って実現する。 そして、自分の手を差し伸ばして、次代の手につないでいこうとする。
 月に照らされた平和祈念像の左手に、平和への強い意思を感じました。
月に照らされた平和祈念像の左手に、平和への強い意思を感じました。
長崎から島原に迂回して、そびえる雲仙岳を眺めながら、フェリーで熊本に入りました。 そこには、27年ぶりに再会する知り合いのご夫婦が待っていてくれました。 4月の地震の時には、近くの小学校に避難して、余震でおびえる夜を過ごしていました。 そのご夫婦、また熊本を見舞うことが今回の旅のもう一つの目的でもありました。 フェリー乗場では、観光客が激減している実状を伺ったり、瓦が崩れ落ちた熊本城を訪れました。 しかし、27年前と変わらない元気なお二人を拝見して、また隣人のために忙しくされているお姿に励まされました。 そして、二人の息子さんは、二人ともお父さんを継いで医者となっていることを伺いました。 世代を越えて、人から人へつないでいく。人それぞれに授かった分があります。 それは自分の会社、自分の家族、自分の街、自分の国なのでしょう。 そこで、先人たちを見上げて、精一杯自分の力を尽くしていく。 それが次代を担う子供たちの道標となるばかりか、周りの人たちを照らす光ともなるのでしょう。 傷痕残る夜の熊本空港。くまモンのぬいぐるみを妻へのお土産に買い求めて、九州を後にしました。