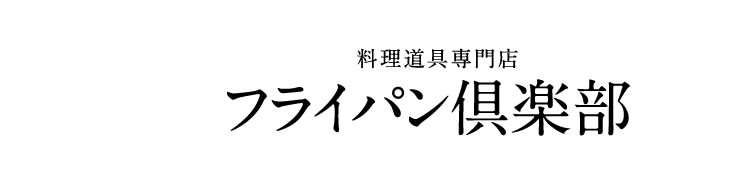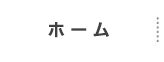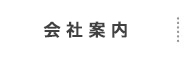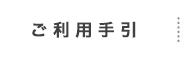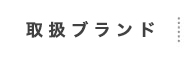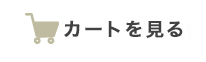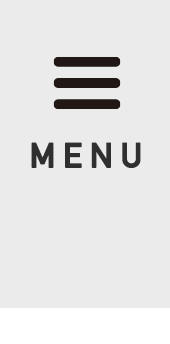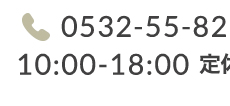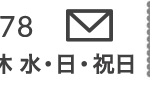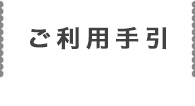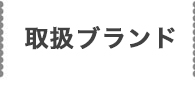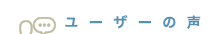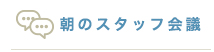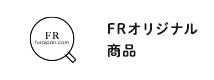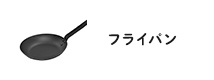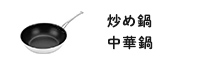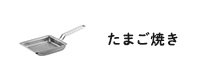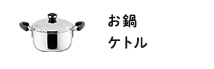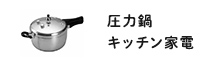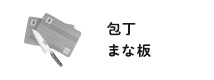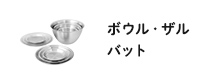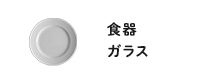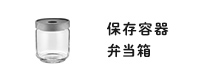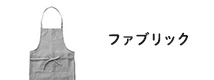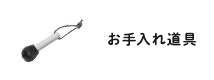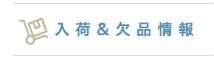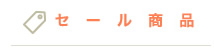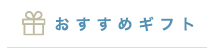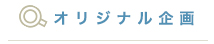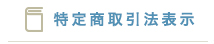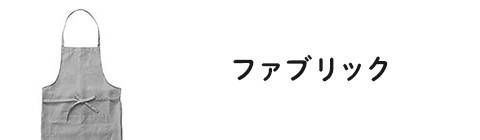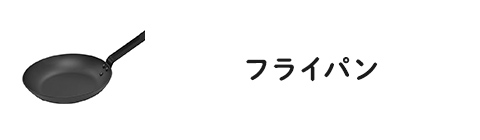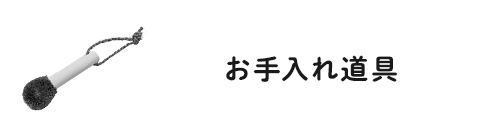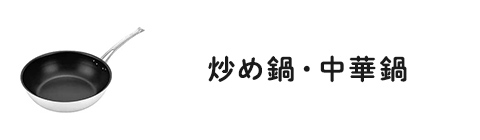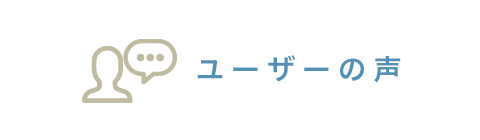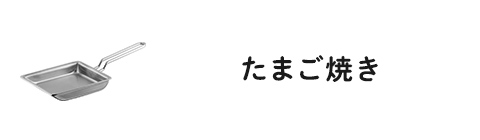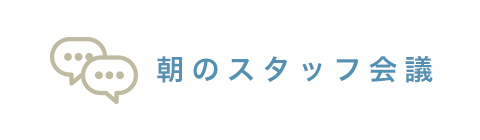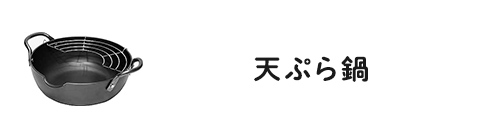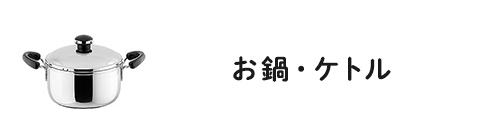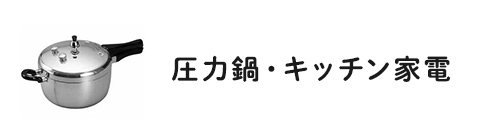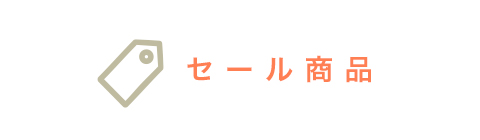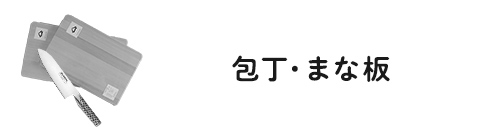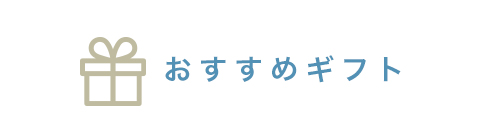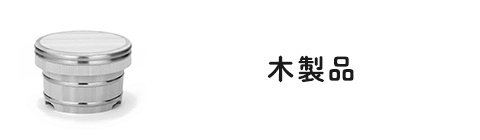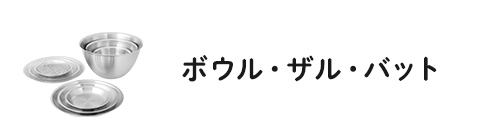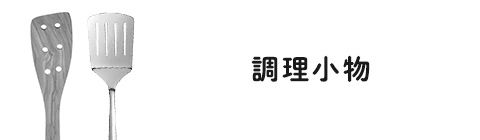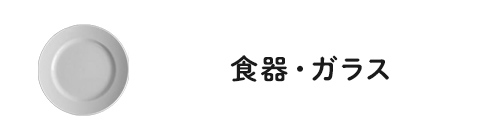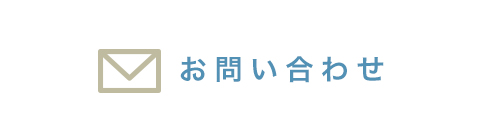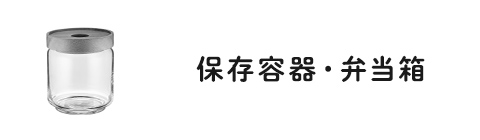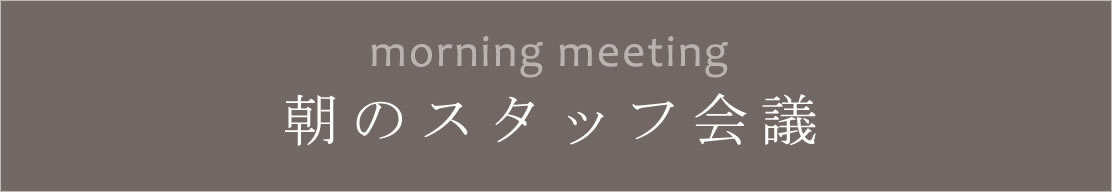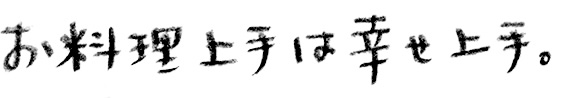ロングセラーの取り箸
筍(たけのこ)のシーズンを迎えて、竹を使った製品を見直しています。 竹製品を扱う雅竹(みやびたけ)さんのページでは、竹のことが詳しく紹介されています。 そこで、目に留まったのが、竹の生育の早さです。 筍として生まれて1年で7~8メートルになる。 一昼夜で120㎝ほど伸びた記録もあるそうです。 寿命は8~10年ほどで、肉質や表皮部分の密度が製品作りに最適なのが3~5年生とのこと。 そして、出来上がってくる製品の一つが アイザワ工房ちゅうぼうこもの取り箸です。 実は、こちらの品は、長期間に渡り安定的によく売れているロングセラー品でもあります。 ここで、この商品がなぜ支持されているのか。 まず、取り箸という商品自体が、お台所で出番の多いアイテムであり、 ほぼ毎日使用するレベルのものかもしれません。 頻繁に使用するのなら、やはり使いやすいものが相応しいでしょう。 その使いやすさは、竹という素材の軽さに由来します。 軽いから握りやすく、さばきやすい。 そして、こちらは煤(すす)竹加工が施されていますので、 カビが生じにくく衛生的です。また、竹の筋目の入った茶色の風合いも魅力です。

 軽くて衛生的な取り箸です。先端は細かいものでもつまみやすい形状となっています。
軽くて衛生的な取り箸です。先端は細かいものでもつまみやすい形状となっています。
筋目模様や色合いは商品によってすべて違い、大変個性的でもあります。 ここで、煤(すす)竹加工についてもご説明いたします。 もともとは、茅葺(かやぶき)屋根の梁(はり)として使われている竹が 50年100年と暖炉裏の煙でいぶされて、濃茶色に変わるものを煤(すす)竹と呼んでいました。 また、最近では、人工的に加工した竹も煤竹と呼んでいます。 【その加工法とは】3~5年生の竹をステンレス製の圧力丸釜に入れて 高圧蒸気を吹き込みながら約1時間で蒸し焼き状態の竹になります。 それを乾燥させたものを炭化竹、通称、煤竹と呼びます。 蒸気を吹き込みながら加工しますので炭にはなりません。 【その特徴とは】高圧で蒸し焼きしますので、竹の内部まで濃茶色なります。 更に竹の中に含んでいた栄養分(主に糖分)や水分がほとんどなくなりますので 虫食いやカビの発生が抑えられます。 製品化した時に茶色になりますので使用後の汚れも目立ちにくくなります。

 上半分は握りやすく丸く、下半分はつかみやすく四角い構造となっています。
上半分は握りやすく丸く、下半分はつかみやすく四角い構造となっています。
さて、この取り箸をよく見ていただくと、上半分の握る部分は丸く、 下半分の箸先までは四角で混在した形状となっています。 そのため、握ると角のないため握りやすく、そして置いてもコロコロと転がって行きません。 頭は、斜めに削られていてワンポイントとなっています。 箸立て等で他の箸とごっちゃになっていても、その頭で見分けることもできます。 また、この30cmという長さが、長すぎす短すぎす、家庭用には相応しいと スタッフたちも太鼓判をおしています。また、細すぎず太すぎず、太さも程よい。 この季節、竹製品を見直してみて下さい。 もしかしたら、筍(たけのこ)として食べるはずだったものが、 取り箸に変わってしまったのかもしれません。 この取り箸の活躍を知れば、たとえ筍を食べ逃してしまっても、 ほっと胸をなでおろすのかもしれません。